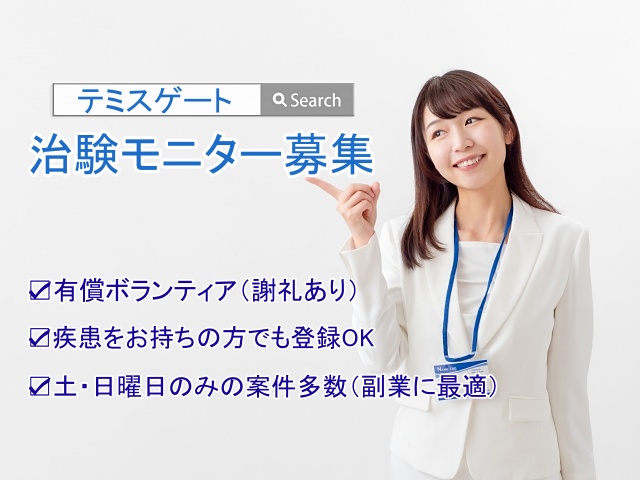『副業で治験モニターしたいけどデメリットってある?』
『薬の治験バイトってヤバくない?』

こんにちは、吉宮です。
治験のアルバイトは、特別な資格や経験がなくても、参加するだけで高額報酬が得られると、今とっても注目されています。
ただ、「そんなうまい話・・・あるわけないよな」「絶対、ウラがある」と、常識ある社会人なら、ついつい警戒してしまいます。
ただ、警戒しつつも高額報酬が気になってしかたないのも本音、ですよね。
そこで今回は、治験のアルバイトをやってみようかなと考えている方のため、治験バイトにはどのようなメリット・デメリットがあるのかを解説いたします。

ちけんのアルバイト~ってどんなの?
治験バイトとは試薬のバイト?

治験バイトとは、ざっくり言うと製薬会社が開発した新薬のデータ採取に協力するボランティア活動のことです。
データ採取が終了すると、企業から協力金としてまとまった金額を受け取るため、治験ボランティアの仲間内では「治験バイト」と呼ばれています。
実際は有償ボランティアです。

有償というのは、謝礼があるということです。
医療ボランティアとも呼ばれていますよ。
昔は「薬の人体実験」などとささやかれていましたが、現在は多くの方がボランティアとして治験モニターに参加しています。
実際の治験モニターはお薬だけでなく、健康食品や健康グッズ、化粧品など、種類はいろいろあって、どれに参加するかは自分で選べるようになっています。
- バイト(仕事)ではなく有償ボランティアです
- 治験に協力する活動を「治験ボランティア」「医療ボランティア」などと呼びます
- 治験の参加者を「治験モニター」と呼びます
高額な報酬はどこから出てる?
治験バイトでは数十万円という高額報酬を受け取ることになりますが、これらのお金の出所は治験を実施した各企業(主に製薬会社)から支払われています。
なので、決して怪しいお金ではなく、危ないことをさせられることと引き換えの高額報酬でもありません。
学生には高額に思えても、社会人にとっては時間換算すると「やや少なく」、確かにボランティア活動ということがわかります。
この報酬は、治験に協力してくれたモニターさんの負担を減らす目的で支払われるため、正しくは「負担軽減費」と言います。
決して「バイト料」とか「報酬」などとは言いませんので、ご注意くださいね。

現在、募集されている治験モニターの種類や、報酬金額などについてはこちらの記事にまとめています。
治験モニターって やってみたいんだけど、ちょっと不安 副作用とか大丈夫? 「高額報酬のバイト」とよく言われる治験モニターですが、実際は有償ボランティアです。 ただ、何をしているの …
治験バイトには「入院」と「在宅」があって自由に選べる!?

治験バイトには、大きく分けて2つのタイプがあり、そのどちらかを選んで治験モニターになります。
- 在宅・日帰りタイプ(短期~長期/日常生活のまま定期的に通院する)
- 入院タイプ(期間は長め/治験期間中は入院・宿泊する)
どちらを選ぶかは、自由です。
在宅で治験バイトをしたい方は、在宅・日帰りタイプの中から治験を選ぶといいでしょう。
また、日帰り一日だけの治験バイトもあるので、休日を有効利用したい方に人気です。
逆に、まとまった時間があって、しっかり稼ぎたいという方には看護師のサポートがある入院タイプの治験バイトが向いています。

長期入院タイプの治験には、夏休みを利用した大学生や、有給利用の社会人なども多いみたいですよ。
どのような治験を選ぶかは完全に自由なのですが、無理なく参加できるものを選ぶことがコツです。
どちらを選んでも、治験モニターの役割は、正しいデータ採取のための協力です。
そのために治験モニターが守るべきルールがあり、それが人によってメリットでもあり、デメリットになります。
治験バイトのメリット・デメリットとは?

治験バイトで、モニター参加した際のメリットとデメリットを見てみましょう。
20代~60代までの治験バイト経験者(67人)からの聞き取りと、治験サイトの口コミ評判から主なものをまとめてみました。
治験バイトでメリットと感じたこと

- 謝礼金が本当に高額で満足した
- 検査以外、特になにもしなくてもよかった(入院タイプ)
- 検査以外、自由時間が多くてオンラインゲームを堪能した(入院タイプ)
- 新商品(健康食品・化粧品など)が無料で試せた
- 新しい薬が使えた(疾病モニター)
- タダで健康診断してもらえた
- 専門医から重要なアドバイスがあった
- 参加するだけで社会貢献になるのがうれしい
- 人付き合いが苦手でもできるボランティア
治験バイト経験者の全員が、謝礼金に関しては「大満足」「満足」という回答でした。
実は、この高額に思える謝礼金ですが、時給換算してみると「まあ・・・そんなものか」という金額なのですが、余暇で得る副収入としてはホクホク顔の満足感があるようでした。
また、治験モニターは金銭的な自己負担は生じないので、「損なし」という点での気楽さもメリットとしてあるようです。

次は、デメリットですね
治験バイトでデメリットだと感じたこと

- 決められた時間に用法・用量を守って使用するのが、けっこうしんどい(在宅・日帰りタイプ)
- 決められた日に、検査のために通院しなければならない(在宅・日帰りタイプ)
- 日記のように記録をつけさせられるのがめんどくさかった(在宅・日帰りタイプ)
- 検査で採血(血液検査)が多かった
- 就寝時間に制約があった(入院タイプ)
- 時間と行動の自由がかなり制限された(入院タイプ)
- 副作用などが出る可能性にビクビクした・発熱した・むくんだ
- プラセボ(偽薬)グループだったかもしれない
この中から、気になるデメリット「採血」「副作用」「偽薬」について、もう少し説明いたしますね。
治験バイトは採血の回数が多い
治験バイトは採血が多い、というのは本当です。
特に入院タイプの治験モニターさんは一日に複数回、血液検査を行うことも多いので、採血(注射)が苦手な方にとっては、精神的苦痛を感じるようです。
この採血の多さに驚いて、治験バイト終了後に「治験バイトは、まじヤバいぞ」と連呼している方は確かにいます。
どうしても採血がダメという方は、採血不要の治験を探してみてください(少ないながらもあります)。
新薬の治験バイトは副作用がこわい
新薬の治験バイトには、確かに副作用の可能性はあります。
「副作用があるかも」と聞くと怖いですが、副作用にもいろいろあります。
例えば、市販の風邪薬、花粉症の薬の注意書きには、副作用として「眠気、だるさ、腫れ、かゆみ・・・」などもふくまれ、記載されています。

眠気が出るものは、車を運転する前に飲んではダメですよ~。
また、化粧品や健康食品などでも、体質によっては「発疹」や「皮膚のかゆみ」など、アレルギー反応のような症状が出るケースも可能性としてはあります。
つまり、副作用には命に関わる重篤なものから、眠気がするなど軽微なものまでさまざまある、ということは知っておきたいですね。
もっとも日本の治験では、モニター参加者の安全性は高いレベルで守られるよう法律で定められています。
万が一、重篤な症状に陥り後遺症が残ったり、死亡するような最悪のケースでは、製薬会社から手厚い補償が約束されています。

もちろん、そんなことが起こらないようにモニター選考の段階から、がっちがちに健康チェックされますけどね。
こういった副作用については、治験ごとの事前説明会で明らかにされるので、それを聞いてから参加するかどうかを決める方も多いです。
安全な試薬の治験バイトもある?

100%安全・安心な治験バイトも中にはあります。

どういうこと?
お薬の治験では、場合によってはニセモノの薬(プラセボ)が使われている可能性もあります。
プラセボが使用される理由は、本物の薬(新薬)の本当の効果を厳密に知るためです。
「病は気から」と言われるように、お菓子のグミでも「これ最新の薬でよく効くんですよ」と言われて食べていると、「治った気がする」「最新の薬だからか、よく効いた」という現象が一定の確率で起こるそうです(プラセボ効果)。
新薬の治験では、プラセボ効果ではない「薬」の本当の効き目を知るために、あえて本物グループと偽物グループとに分けて行うこともあります。
ただ、自分がどちらのグループに入っているかは、判断がつきませんし、医師さえも知らされていないこともあります。
このプラセボ(偽薬)ですが、内容は健康やデータに影響しないビタミン剤や小麦粉などの食品でできていたりするので、何の効果もないかわりに副作用もありません。
ある意味、安心安全の治験バイトかもしれませんね。
治験バイト「入院」と「在宅」で違うデメリットとは?

治験バイトを始めると、入院モニターか在宅モニターかで、それぞれ決まり事があります。
この決まり事が、人によってはデメリットに感じることもあるようです。
入院モニターと在宅・日帰りモニターの違いをチェックしておきましょう。
治験バイト「在宅・日帰り」モニターの決まり事とは?
在宅・日帰りモニターの治験バイトでは、日常生活を送りながらモニター生活を送り、決められた日時に通院して検査を受けるというスタイルで行われます。
特に在宅モニターには正確なデータ採取のため、ルールが課せられることが多いようです。
- 決められた用法・用量を守って治験薬や商品を使用する必要がある
- 指定された日時に病院で検査を受ける必要がある
- 行動を制限されることがある(禁煙や飲酒の制限、運動の制限など)
- モニター記録(日記形式)の提出を課されることもある
治験バイトの入院モニターの決まり事とは?
入院モニターの治験バイトでは、医療施設に宿泊して行われます。
入所後は原則、カンヅメです。
治験終了日まで外出できず、他人との共同生活がストレスに感じることがあります。
- 治験期間中の外出・面会制限がある
- 他の治験モニターとの共同生活となりプライバシーが保ちにくい
- 起床時間・就寝時間が決まっている
- 空調の温度調節が自由にできない
- 自由な飲食ができない(買い食い・持ち込みNG)
入院タイプの治験バイトは、検査の時以外は、施設内であれば自由行動がゆるされていますが、外出はできません。
そのため、施設内には図書室や遊戯室があり、DVD、ゲーム機なども準備されています。

スマホ持参で、思う存分ゲームを楽しんでください。
ただし、起床時間~就寝時間までスケジュール管理されているので、寝坊や夜更かしなどはできません。
このところ「治験バイトやってみようか」という方が増えていますが、実際どんなことをしているのかわかりにくいため、「治験バイトってやばいやつだろ?」「おまえ、それ大丈夫?」などと周囲に心配されます …
【治験バイト】おすすめサイトはどこ?
治験バイトを探すなら、まずは信頼のおける治験モニター登録サイトにモニター登録をします。
ここで注意したいのは、登録後に金銭的な自己負担が発生しない募集サイトを選ぶことです。
本来の治験モニターは有償ボランティアなので、金銭的な持ち出しはありません。

紹介手数料とか検査費用とか、何かとお金を払わされる会社はニセモノです。
ここでは参考までに、初心者でもチャレンジしやすい治験モニター登録サイトを2件ご紹介いたします。
どちらもモニターの安全性重視・お金の自己負担などは一切なしの治験モニター募集サイトです。

ここからは、治験モニターを募集する会社のPRです。
詳細は、それぞれの公式HPや担当者にご確認くださいね。
1位 テミスゲートの治験モニター募集サイト【PR】

- 20~80歳までの男女を幅広く募集しています。
- 日帰りや土・日限定の治験案件もあります。
- 初めての方でも安心して取り組める丁寧なサポートがあります。
- 報酬の受け取りは「振込」か「手渡し」が選べます。
- モニター登録後、医薬品や健康食品、化粧品の治験の案内がメールで届くので選びやすい
初めての治験モニターという方なら、テミスゲートからスタートするのもいいでしょう。
テミスゲートは比較的、初心者が取り組みやすい短期・日帰り・在宅・日帰りタイプの治験案件を取り扱っています。
さらに、土日限定の治験などもあるので、仕事をしながらちょっとしたお小遣い稼ぎができるのも、うれしいですよね。
もちろん、本格的に取り組みたくなれば、長期・入院タイプの治験も紹介してもらえます。
そうやって、経験を重ねて信頼度がアップすれば、テミスゲート側からクローズドの特別案件の打診も来たりするようです。
初心者からベテランまで、ていねいなサポートをしてくれるのが、テミスゲートです。
2位 シスモール(コーメディカルクラブ)の治験モニター募集サイト
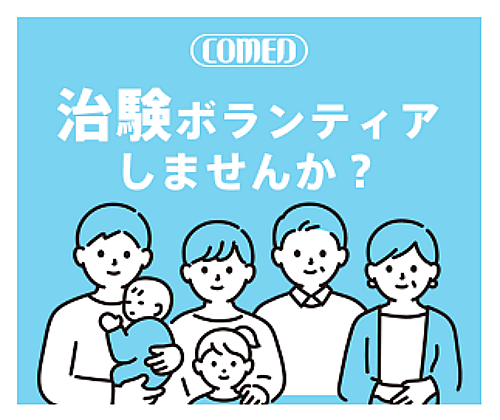
- 20歳以上の男女を対象とした治験モニターを募集しています。
- 関東⇒東京、神奈川、埼玉、千葉の方限定
関西⇒大阪、兵庫の方限定 - CRCとしても実績ある大手治験サイトで、サポート体制も万全です。
- 初心者でも参加しやすいようにサポート体制もあり、治験施設も充実しています。
- 定期検診も無料実施しています。
シスモール(コーメディカルクラブ)は東京と大阪を拠点とした治験サイトで、関西在住の方でも参加できる案件が多いのも強みです。
もちろん短期・在宅・日帰りタイプの治験案件もありますが、どちらかというと本格的に取り組みたい方に向いているかもしれません。
体調の変化が気がかりな人でも、治験モニターに参加すればお金を掛けずに検査が受けられ、専門医からのアドバイスもあります。
大阪・兵庫県にお住まいの方や、本格的に治験モニターに取り組みたい方などにおすすめの安定した治験サイトです。
まとめ

今回は、治験バイトを始めるにあたってのメリット・デメリットをまとめてみました。
治験バイトを経験した方々に聞き取ったところ、誰もが口をそろえて「採血の多さ」をデメリットとして挙げます。
副作用では、服薬後にだるさや軽い眠気を感じた、という方はそこそこいるようでしたが、(私たちがアンケートを採った方々は)あまり気にしている感じではありませんでした。
それ以外のデメリットとしては、やはり治験ごとの決まり事でしょうか。
起床・就寝時間を守らねばならないことや、「~してください」「~しないようにお願いします」という行動制限に多少なりともストレスを感じるようです。

これに慣れる方は治験バイトを続け、ムリな方は一回きりでやめていますね。
治験バイトをする際は、まず向き・不向きを考えた上で選ぶと、長く楽しんで続けることができるのだと思います。
『治験バイトしたいんだけど、どこで申し込むの?』 『治験バイトって在宅でもできるの?』 治験バイトに関心があってチャレンジしてみようかな、と考えている方に初心者でも …